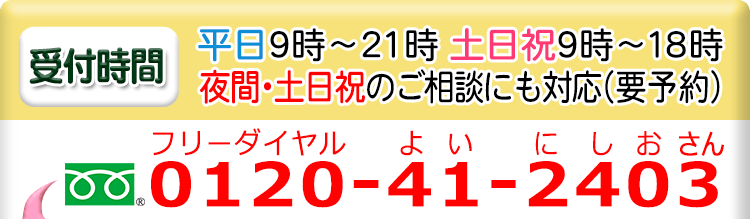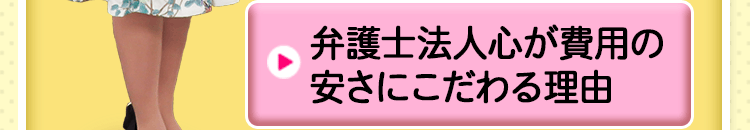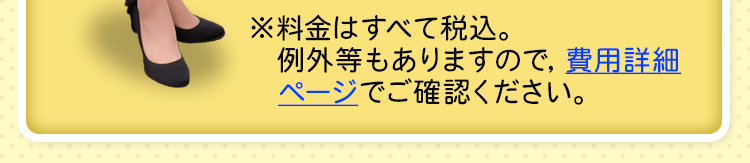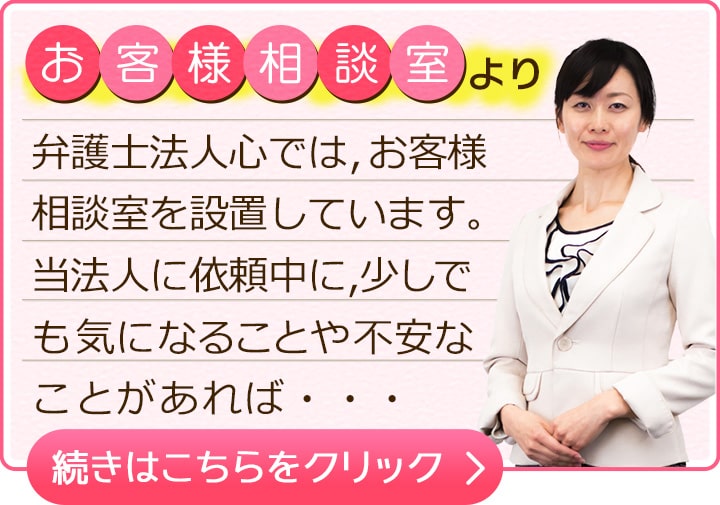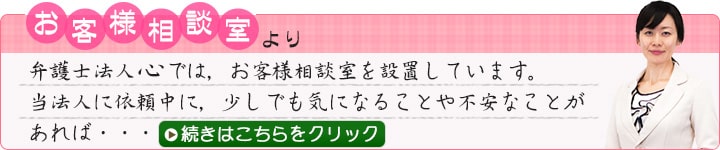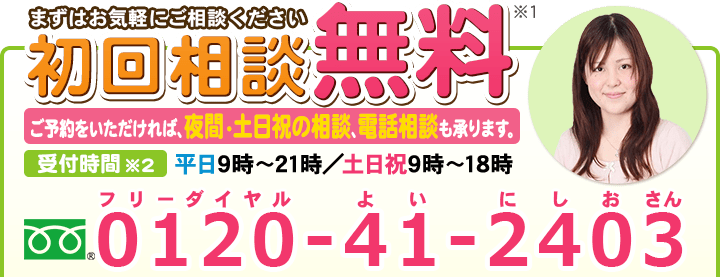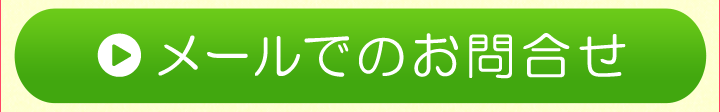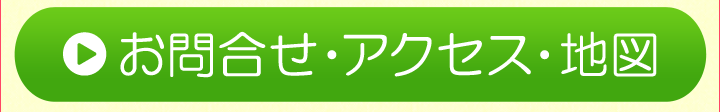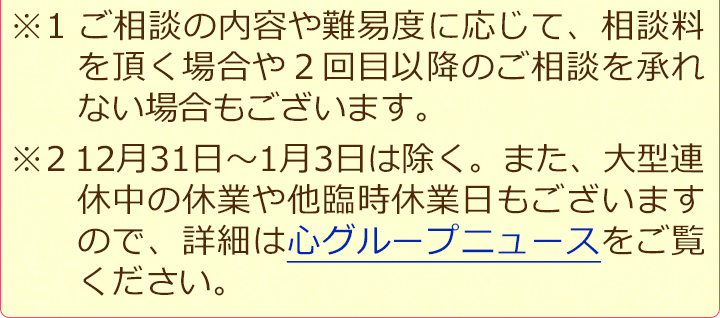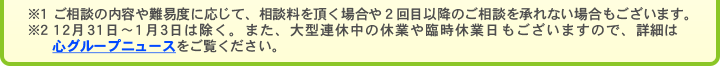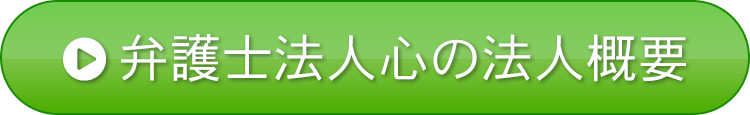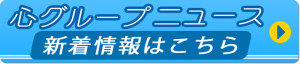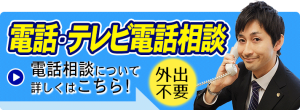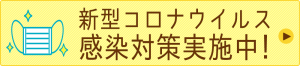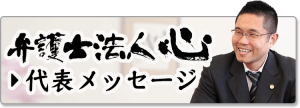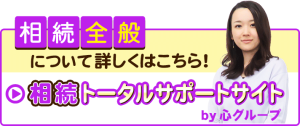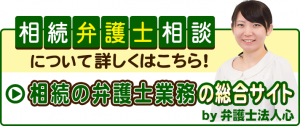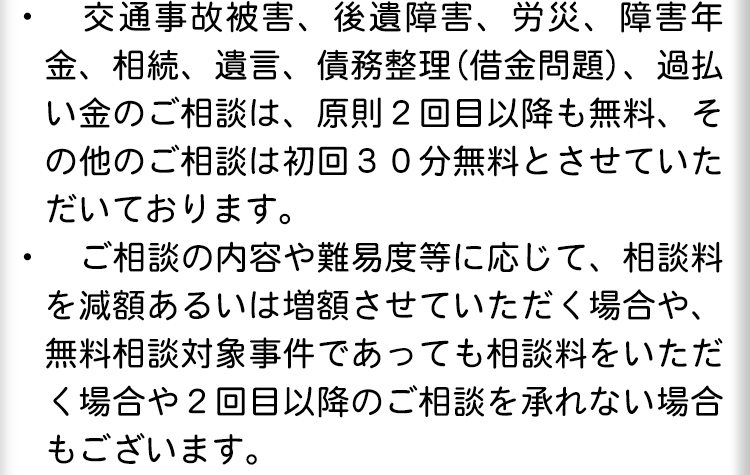
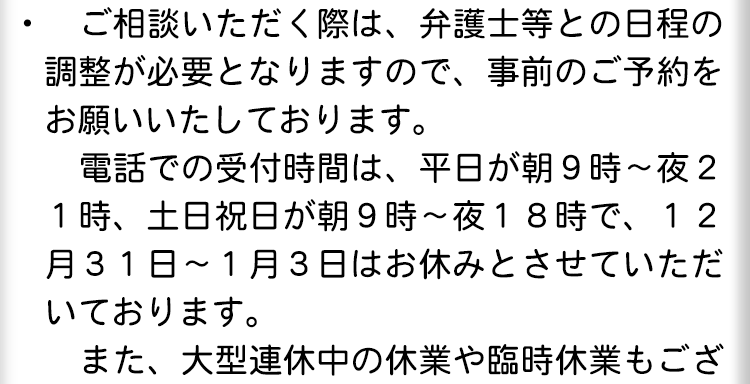
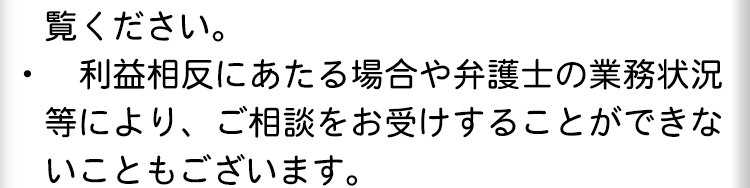

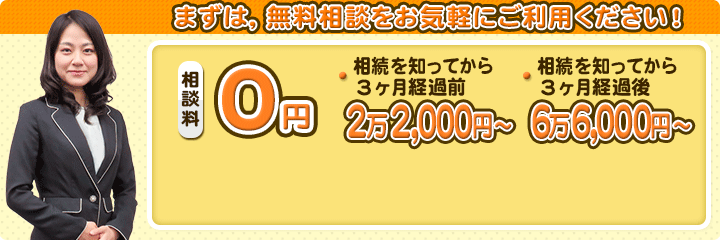
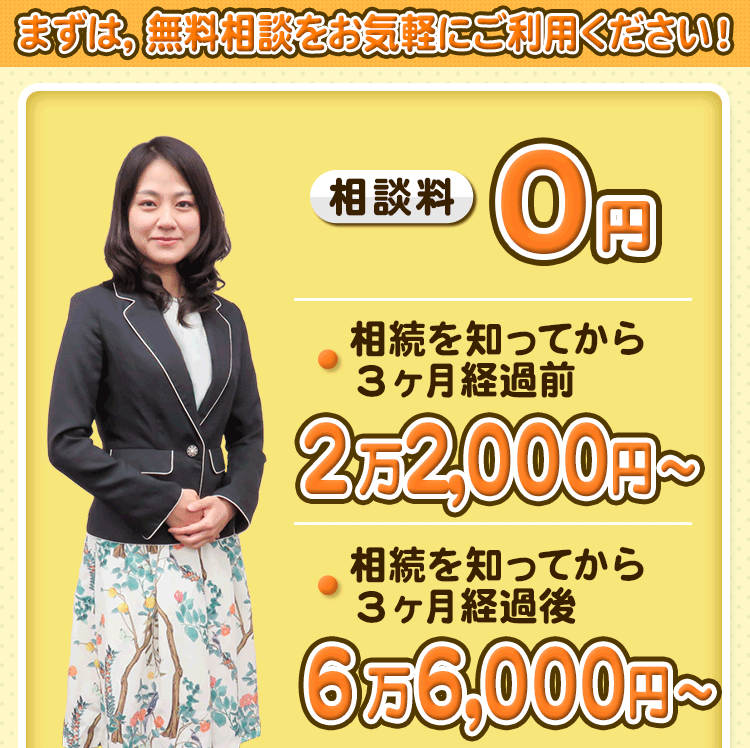
相続放棄での弁護士と司法書士の違い
1 相続放棄手続きの性質

相続放棄は、家庭裁判所に所定の書類と付属資料を提出し、家庭裁判所がその内容を審査したうえで、相続放棄を認めるべきと判断した場合に受理されることで成立する手続きです。
専門用語で表現をしますと、家庭裁判所が認めることで成立する手続きなので、「審判」といいます。
この手続きの代理人となれるのは、原則として弁護士のみです。
もっとも、実際には、司法書士の方が依頼を受けて相続放棄を行っていることがあります。
これについて、弁護士とどのような違いがあるか、説明します。
2 手続代理人として相続放棄ができるか否か
相続放棄手続きの代理人になれるか否かは、形式的には、相続放棄申述書(相続放棄をする際に裁判所に提出する書面)において、実際に相続放棄をする方(申述人)の手続代理人として名前を記述できるか否かという違いがあります。
弁護士であれば手続代理人として記載できますが、司法書士の方の場合、記載ができません(申述人名義での、書類作成の「代行」のみができるという形になります)。
そして、この違いは、実務上、次のような違いを生みます。
相続放棄は、相続放棄申述書とその付属書類を提出しただけでは完了しません。
家庭裁判所は、書類等を受け取ると、相続放棄を認めてよいかどうか、内容を審査します。
書類について不明点がある場合や、詳しく確認したい点がある場合、手続代理人がいれば手続代理人に連絡をします。
そして、手続代理人である弁護士が、専門知識に則り、対応します。
手続代理人がいない(相続放棄申述書に手続代理人の記載がない)場合には、申述人本人に連絡がなされるため、本人対応が必要となります。
対応次第では、相続放棄が認められなくなる危険性もあります。
また、家庭裁判所は、相続放棄を認めてよいか否かを判断するため、相続放棄の申述が真意に基づくものであるか、法定単純承認事由がないかを確認するための質問状を送ることがあります。
申述人本人に送られることもありますが、手続代理人がいる場合には、手続代理人に送付することがあり、手続代理人による対応が可能です。
また、手続代理人がいる場合には、そもそも質問状を送らないという運用をしている家庭裁判所もあります。
このように、弁護士と司法書士の方の違いは、手続代理人になれるか否かであり、相続放棄申述書提出後の、申述人の負担に大きな違いがあります。

相続放棄を弁護士に相談するタイミング
1 弁護士に相談するタイミングは早いほどよい

相続放棄を弁護士に相談するタイミングに決まりはありません。
しかし、確実にいえるのは、早いほど良いということです。
なぜなら、相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないという、極めて短い期限が設けられているためです。
期限が近くなってしまうと、弁護士であっても対応が不可能になることさえあります。
また、法定単純承認事由に該当する行為をしてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
法定単純承認事由は、故意に行うことは少なく、知らなかったがゆえにうっかりやってしまうというケースがほとんどです。
そのため、早めに弁護士に相談し、法定単純承認事由に該当する行為の説明を受けることで、相続放棄が認められなくなる可能性を減らすことができます。
2 相続の開始前からでも相談すべき
相続放棄の手続き自体は、相続の開始後、つまり被相続人が死亡した後でなければできません。
しかし、被相続人となるべき方がご存命のうちであっても、相続放棄をすることを検討されているのであれば、弁護士に相談すべきです。
その理由は、相続放棄を行う際に問題となる財産、契約関係の事前整理ができるためです。
例えば、被相続人となる方が多少の現金、預貯金を持っている場合、ご存命のうちに相続人となる方へ贈与してしまうことができます(相続開始後は、相続放棄を前提とする場合、取得することができません)。
被相続人となる方が賃貸住宅に住んでいる場合、ご存命のうちに解約または賃借人名義変更をし、かつ残置物を処分してしまうことで、相続放棄後のトラブルを軽減できます。
電気、ガス、水道、携帯電話の契約などについても、事前に解約または名義変更をしてしまうと、相続開始後に発生する問題を回避できます。
自動車がある場合も、相続開始後の処分は困難になるため、ご存命のうちに名義変更または売却・廃車処分をしてしまうことができます。

相続放棄でかかる費用
1 相続放棄手続きそのものに要する費用
相続放棄は、裁判所に対して相続放棄申述書を提出することで手続きが開始されます。
相続放棄の際に最低限必要な費用は、裁判所手数料として800円分の収入印紙と、予納郵券(切手)数百円分(裁判所によって異なります)です。
2 付随する費用

相続放棄申述書には、付随書類として、申述人の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が子や兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票を添付する必要があります。
これらの収集には、通常数千円要します。
多数の戸籍謄本類を収集しなければならない場合、1万円を超えるケースもあります。
3 専門家に依頼する場合
専門家に依頼する場合、一般的には数万円~十数万円です。
費用はサービスの内容や、難易度によっても変わってきます。
弁護士以外の専門家による場合、単に相続放棄申述書の作成を代行するのみとなりますので、費用は低くなる傾向にあります。
もっとも、作成代行ですので、あくまでも申述人本人の名義で相続放棄鉄続きを行うことになります。
そのため、相続放棄申述書を提出した後の裁判所とのやり取りは、基本的には全て本人が対応しなければなりません。
弁護士の場合、「代理人」となることができます。
そのため、申述人ご本人に代わって、裁判所とのやり取りについて窓口になることができますので、他の専門家と比べ、サービスの質が高い分、金額的にはやや高くなる傾向があります。
事件の難易度によっても、費用が変わります。
たとえば、被相続人が死亡してから3か月を経過している場合、「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨の説明を、しっかりとした書面を作成したうえで裁判所に説明する必要があるため、高い技術が求められることから費用も高くなります。
そのほか、相続放棄が受理された後、被相続人の債権者に対して、相続放棄を終えた旨の連絡をし、今後の請求や連絡を止めるというサービスを行う場合は、オプション料金が必要となることもあります。

相続放棄に強い弁護士に依頼する方がよい理由
1 弁護士と他の士業との違い

相続放棄は、弁護士以外の士業の先生が行っていることがあります。
相続放棄手続きにおける、弁護士と他の士業の方との一番大きな違いは、裁判所との関係において、手続代理人になれるか否かです。
そして、弁護士のみが、手続代理人になることができます。
他の士業の方の場合、あくまでも書類作成、提出の「代行」をするにとどまり、代理人を名乗ることはできないため、裁判所からみると、申述人ご本人様が手続きをしているように見えます。
そのため、相続放棄申述書提出後の質問状回答対応や、諸々の裁判所からの問い合わせなどは、すべて申述人ご本人様にて対応する必要があります。
2 相続放棄に強い弁護士
弁護士が対応することができる法律問題は、非常に多岐に渡ります。
すべての分野を深くカバーすることは事実上困難であるため、弁護士にも得意な分野とそうでない分野が存在します。
不得意な分野については、スムーズかつ正確に事案の解決をするのが難しいことがあります。
このことは、相続放棄についてもいえます。
特に相続放棄は、次の理由から、相続放棄に強い弁護士に依頼するべきです。
相続放棄の手続きにおいて、相続放棄申述書を作成して裁判所に提出すること自体は、それほど難しくはありません。
もっとも、相続放棄申述書を提出すると、裁判所から質問状が送られてきます。
この質問状への回答を誤ると、相続放棄が認められなくなるという危険性があります。
相続放棄は一発勝負であり、却下されてしまうと二度とできなくなる可能性がありますので、質問状対応は、相続放棄に精通した専門家を通じて、とても慎重に対応する必要があります。
また、相続放棄の場面においては、申述人の方は、付随する問題について大きなお悩みを持たれていることが多いです。
もっとも多いのは、被相続人が借金を有していた場合の、債権者への対応です。
申述人の方としては、債権者から二度と請求されることはないと確信できて、はじめて問題が解決したことになります。
相続放棄に精通した弁護士であれば、単に相続放棄の手続きをするだけではなく、こうした付随問題への対応知識、経験、ノウハウを有しており、スムーズに解決することができます。

相続放棄の撤回・取消
1 相続放棄の撤回は困難

相続放棄の申し立てを行ったけれども、後々プラスの財産が見つかったため、やっぱり相続放棄を撤回して財産を受け取りたいと思い直す方もいらっしゃるようです。
しかし、相続放棄の撤回が認められる期間は非常に限定的で、撤回するのは非常に困難なものといえます。
法律の規定では、一度相続放棄の申し立てが裁判所に受理された場合には、相続放棄の3か月の熟慮期間が経過していなくても、撤回することはできないとされています。
家庭裁判所の実務上は、相続放棄の申立書類の提出から裁判所の審査が終了するまでの間は撤回が可能という運用にはなっています。
ただし、あくまで内部処理が完了するまでの間なので、撤回したいと思った時に裁判所内部の手続きが終了していたらそれまでとなります。
2 取消しを主張する余地はあるがハードルは高い
例外的に、重大な事実に誤りがあったような場合や、詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまった場合は、取消しを主張する余地はあります。
もっとも、裁判所への訴訟手続等が必要になるため、相続の放棄の取消しが認められるのは非常にハードルが高いといえます。
3 相続放棄が認められなかった場合のやり直しも不可
また、逆に相続放棄の申し立てを行ったが認められなかった場合にも、手続きのやり直しは認められていません。
この場合は、亡くなった方の負債をすべて背負わなければならなくなります。
4 相続放棄の相談はお早めに弁護士へ
このように、相続放棄は一度手続きが進みだしたら容易にやり直しのきかない手続であるため、相続放棄をするかしないかを決めるスタートの段階から、早めに弁護士に相談して正確に手続きを進めていくことをおすすめします。
場合によっては、相続放棄の熟慮期間の延長の手続きを行ったり、相続放棄ではなく限定承認を行うという方法も考えられます。
弁護士法人心では、相続放棄の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。相続放棄を考えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

何年も前に亡くなった方の借金が発覚したら
1 相続放棄の類型

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行うこととされています。
そのため、被相続人がかなり前に亡くなっていたとしても、そのことを知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをすればよいことになります。
もっとも、一般的には、相続の開始は、被相続人死亡日か、その数日後に知ると考えられています。
そのため、被相続人死亡日から3か月以内か、3か月以上経過しているかで、相続放棄手続きの際の裁判所に対する対応は変わってきます。
3か月以内の場合は特段の必要はありませんが、3か月を超えている場合は、被相続人の死亡を知った経緯等をしっかりと書面で説明します。
典型的なケースとしては、何十年も前に離別した親が借金を抱えたまま亡くなっており、借金の債権者から相続人に対する支払いを求める通知書面等を受け取ってはじめて被相続人の死亡を知るというものがあります。
このとき、すでに被相続人死亡から3か月以上経過していることがほとんどです。
2 被相続人の死亡から5年以上経過していると
上記のとおり、被相続人死亡から3か月以上が経過していても、相続の開始を知った経緯をしっかり説明できれば、相続放棄の手続きはできます。
しかし、被相続人死亡から5年以上が経過してしまっている場合には、かなり面倒なことになる可能性があります。
相続放棄の手続きを行う際、被相続人の最後の住所地を示すための書類として、住民票除票または戸籍の附票を提出する必要があります。
相続放棄の手続きを行える裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所であるためです。
しかし、被相続人が死亡してから5年以上が経過してしまうと、住民票除票または戸籍の附票が廃棄されてしまうことがあります。
この場合、裁判所に対して、住民票除票または戸籍の附票が廃棄されている旨を報告したうえで、業務連絡を記した書類を発行してもらいます。
その後、被相続人の本籍地を管轄する法務局に対し、裁判所の業務連絡書面を示したうえで、被相続人の死亡届の記載事項証明書というものを発行してもらわなければなりません。
この死亡届の記載事項証明書には、被相続人の最後の住所地が記載されているので、これを以て、住民票除票または戸籍の附票の代わりとするのです。

ご存命のうちからの相続放棄の準備
1 相続放棄は、ご存命のうちに行うことはできない

まず、前提となる事項について説明します。
被相続人となる方がご存命のうちには、相続放棄をすることはできません。
相続放棄は、相続が開始されていることが要件とされています。
相続は、被相続人がお亡くなりになった時点で開始されます。
そのため、被相続人がお亡くなりになるまでは、相続放棄は行えないことになります。
似たような制度として、遺留分の放棄というものがあります。
遺留分の放棄は、被相続人となる方がご存命のうちに行えますが、要件が厳格であり、裁判所による許可が必要です。
2 生前から準備を行うことはできる
実際には、被相続人となる方がお亡くなりになったら、すぐにでも相続放棄をすべきケースはあります。
たとえば、被相続人となりうる方がご存命のときから、負債を多くお持ちでいらっしゃることが判明している場合です。
このような場合、あらかじめ相続放棄の準備を進め、円滑な手続きを行えるようにしておくことはとても大切です。
特に重要なことは、不動産や自動車の処分と、賃貸物件にお住いの場合は残置物の処分です。
これらは、被相続人死亡後に残っていると、相続放棄との関係では非常に面倒な存在となるためです。
相続放棄をする場合、原則として被相続人の財産を処分することはできません。
他方、相続財産に関しては、管理責任というものを負います。
不動産、自動車、残置物については、処分することができず、相続財産管理人選任の申立てをしない限り、管理責任のもとで保全を続けなければならなくなります。
建物がある場合、被相続人死亡後に相続放棄をすると、いつまでも管理責任のもとで補修等を行わなければならない可能性がありますので、生前に取り壊しておきたいところです。
自動車は、相続放棄をする際、かなり悩ましい物の一つですので、可能な限り廃車処分または売却をしてしまうとよいです。
被相続人となる方が賃貸物件にお住いの場合、あらかじめ残置物となり得る物は処分します。
可能であれば、賃貸借契約も解約した方が良いです。

被相続人がお亡くなりになってから3か月以上経ってしまっていたら
1 まずは状況の確認から

被相続人死亡から3か月以上経過していたとしても、まだ相続放棄をすることができる可能性が残っています。
相続放棄の申述の期限は、被相続人死亡日から3か月ではなく、「相続の開始を知った日」から3か月です。
相続の開始を知った日とは、被相続人が死亡したことと、ご自身がその相続人であることを知った日です。
そのため、被相続人の死亡を知った日が、被相続人の死亡から3か月以上経過した後であっても、それまで被相続人の死亡を知り得なかったのであれば、法律上は相続放棄ができます。
もっとも、裁判所においては、相続の開始は、被相続人死亡日またはその日から数日後程度で知ると認識されていると考えられます。
そのため、事実上は、被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄を行うことが原則となっていると考えられます。
2 相続放棄申述書の作成
被相続人死亡日から3か月以上経過した後になって、被相続人が死亡したことや、ご自身が相続人であることを知った場合、相続放棄申述書の作成には注意が必要です。
被相続人死亡から3か月以内に相続放棄の申述を行う場合、相続放棄申述書はシンプルなもので大丈夫です。
しかし、被相続人死亡から3か月以上経過している場合には、被相続人の死亡およびご自身が相続人であることを知るのが遅くなった経緯について、相続放棄申述書のなかでしっかりと説明しなければなりません。
たとえば、被相続人と音信不通で没交渉であった場合、被相続人の債権者を名乗る貸金業者や金融機関からの書面を受け取って、はじめて被相続人死亡を知るということがあります。
このような場合、債権者の連絡書面の写しを以て、被相続人死亡を知った日を疎明します。
また、被相続人と疎遠で没交渉であったことも疎明し、被相続人の死亡や財産状況を知り得なかったことも説明します。

相続放棄をするべきか遺産を取得するべきか
1 遺産の取得とは

被相続人がお亡くなりになると、相続が開始されます。
一般的には、相続が開始されたら遺産分割協議を行い、被相続人の財産(相続財産)を相続人間で分割するということの方が多いと思います。
具体的には、法定相続人や相続財産・相続債務等を調査したうえで、どの財産をどの相続人が取得するかを話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載して、各相続人が署名・押印をするというものです。
そして、遺産分割協議書を用いて、相続財産に含まれる不動産の登記を移転したり、預貯金や有価証券の名義変更・解約を行うという流れになります。
2 相続放棄と法定単純承認事由に該当する行為
相続放棄は、法律上、初めから相続人ではなかったことになるという効果が発生する手続きです。
相続人でなくなる以上、相続財産を取得する前提、および相続債務を負担する前提を失います。
つまり、相続放棄と遺産の取得は両立しないものといえます。
ここで、「法定単純承認事由に該当する行為」というものについて説明します。
法定単純承認事由に該当する行為とは、行ってしまうと、相続放棄をすることができなくなる行為のことです。
相続財産の処分は、法定単純承認事由に該当する行為のひとつとされています。
そして、遺産分割協議を完了させることや、遺産の取得は、相続財産の処分にあたると考えられています。
遺産分割協議を完了させる行為は、遺産を取得するという意思の表れとされるため、法定単純承認事由となります。
この観点からも、遺産の取得と相続放棄は、どちらか一方しか行うことができないといえます。
3 相続放棄をするべきか否か悩んでいる場合
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
一般的に、被相続人の方がお亡くなりになられた後に行わなければならないことは多いため、相続放棄は想像以上に非常に短い期間で決断をしなければならない手続きであると考えられます。
被相続人が生前に生活保護を受給して生活していたなど、預貯金などの財産がほとんどないことが明らかであり、むしろ消費者金融等に対する借金のような負債を有している可能性が高い場合などは、悩むことは少ないと考えられます。
問題となるのは、被相続人が預貯金や不動産など、それなりの財産を有しているが、同時に負債も有している可能性があるなど、財産構成が複雑である場合です。
相続財産の調査は簡単ではないため、財産の方が多いのか、負債の方が多いのか、短期間では判明しないことがあります。
特に、被相続人が自営業を営んでいた場合などは、被相続人個人の資産に加え、事業用の設備や在庫商品、売掛金、預貯金等を有している一方で、金融機関からの借入や買掛金等の負債を有していることがほとんどであるため、相続財産の調査にはより時間を要することが想定されます。
このような場合、財産の調査に時間を要する事情が存在することを理由として、管轄の家庭裁判所で、相続放棄の申述期間の延長という手続きを行うことで、被相続人の財産・負債の状況を明らかにした後、必要であれば相続放棄をするということができます。

相続放棄をした方がよいケース
1 相続放棄の効果とメリット

相続放棄をすることで得られる法的効果は、「当初から相続人でなかった」ことになるというものです。
たとえば、親が亡くなった場合に子供が相続放棄をすると、相続に関する法律上(特に財産に関して)は、はじめから子供ではなかったことになります。
感覚としては、被相続人の財産・負債に関しては、全くの他人になるということです。
この効果は、特に相続に関してネガティブな要素が多い場合にメリットが生まれます。
相続放棄をする理由は限定されていませんが、以下、相続放棄をした方がよいケースについて説明します。
2 債務超過
いわゆる、被相続人に借金があり、かつめぼしい財産がない場合です。
相続放棄をする動機としては、実務上最もよく見られるものあると考えられます。
被相続人に借金がある状態で相続放棄をしないでいると、相続人は、法定相続割合に基づいてその借金を背負うことになってしまいます。
被相続人の債務の金額が大きい場合、自己破産等をしなければならなくなるかもしれません。
相続放棄をすると、当初から相続人ではなかったことになりますので、当然相続債務を負うことはありません。
被相続人が亡くなった時には、借金の存在が明確ではないが、過去の被相続人の行動などから、多額、多重の借金をしている可能性があるということもあります。
このような場合も、あらかじめ相続放棄をしておけば将来借金が発覚しても、返済する義務を免れることができます。
実務上は、被相続人の債務額が明確であることは多くありません。
むしろ、疎遠であった被相続人がお亡くなりになり、どこにどのくらいの債務を負っているかがわからないということの方が多いです。
後々、どこからいくら請求されるかわからないという抽象的な不安を解消するために、相続放棄が用いられるということがあります。
3 相続に関わりたくない
被相続人と疎遠で債務等の事情が全く分からない、他の相続人と関係が悪くコミュニケーションを取りたくない、または他の相続人の中に過激な行動等を起こす人がいて遺産分割協議をしたくないということもあると思います。
何十年も没交渉であった被相続人に関する調査をするのは、非常に大変です。
特に相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月というとても短い期限が設けられていますので、その間に疎遠であった被相続人のことを調べるのは簡単ではありません。
また、関係が悪い他の相続人と話をすれば、相続とは無関係なことで不要なトラブルを生んでしまう可能性もあります。
さらに、危険な行動をする可能性がある他の相続人と遺産分割をめぐって紛争が起きたら、危害を加えられるかもしれません。
このような場合、相続放棄をしてしまえば、相続とは無関係になることができるので、相続関係から離脱でき、安心です。

相続放棄における裁判所からの連絡
1 相続放棄は書類を提出しただけでは終わらない

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書や戸籍謄本類等の付属書類を提出することで開始されます。
家庭裁判所が相続放棄申述書を受け付けると、相続放棄申述書の内容についての審査が開始されます。
この時点では、あくまでも、相続放棄の手続が開始されたにすぎず、未だ相続放棄の手続が完了したわけではありません。
家庭裁判所は相続放棄の書類を審査し、必要に応じて申述人(相続放棄をしようとしている相続人)に対して質問状を送付することがあります。
質問状に回答しないと相続放棄の手続きが進みませんので、回答する必要があります。
また、回答の内容次第では相続放棄の手続に影響が出るため、慎重に対応する必要があります。
回答を記した質問状を家庭裁判所に返送すると、引き続き家庭裁判所は審査を行います。
その結果、特に問題がないと判断されれば、相続放棄申述受理通知書が発行され、無事相続放棄手続は終了となります。
なお、相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月とされていますが、これは期限までに家庭裁判所に対して相続放棄申述書や戸籍謄本類等の付属書類を提出すればよいという意味であり、期限までにすべての手続きを終える必要があるという意味ではありません。
2 なぜ裁判所は質問状を送るのか
家庭裁判所が質問状を送る目的は、次の2つであると考えられます。
① 申述人の真意に基づく手続きであるかを確認する
他の相続人が申述人になりすましていないか否かや、他の相続人等から強要された相続放棄ではないかを確認します。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなくなるという法的な効果が発生します。
そのため、他に相続人がいる場合、その相続人の取り分が増えることから、なりすましや強要が発生する可能性があるのです。
そのため、このような確認がされます。
② 法定単純承認事由に該当する行為がないかを確認する
もう1つは、相続放棄が認められなくなる行為(法定単純承認事由に該当する行為)を行っていないかを確認することにあると考えられます。
具体的には、被相続人の預貯金を自分のために費消するなど、財産を処分してしまったり、隠匿していたりしないかを確認します。
被相続人の着古した衣類や、使い古した家財道具などの残置物を処分してしまった場合、それが相続財産の処分に該当するか否かの判断は微妙であることもあります。
被相続人の預貯金や現金の費消については、例外として法定単純承認事由に該当する行為とされないケースもあります。
残置物の処分についても、それが相続財産を構成するか否かという観点から検討する必要があります。
判断に迷った場合は、専門家に相談する方がよいでしょう。

相続放棄の期限について
1 「相続の開始を知った日」から3か月間

相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月間です。
この期間のことを、相続放棄の熟慮期間と呼ぶこともあります。
あくまでも、期限の起算点は相続の開始を「知った日」なので、相続が開始(被相続人が死亡)してから3か月以内ではないことに注意が必要です。
では、相続の開始を知った日について、具体例をいくつか挙げてみます。
2 看取った場合
最も典型的なものは、被相続人がお亡くなりになられた日に知った場合、例えば、看取った場合です。
被相続人がお亡くなりになられた日に知った場合、例えば、看取った場合です。
この場合、被相続人死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。
3 被相続人が死亡した旨の通知を受けた場合
次に、警察や市役所、債権者などから、被相続人死亡の連絡を受けた場合です。
被相続人と没交渉となっていたような場合、相続人の方は被相続人が死亡しても、すぐに知ることは少ないです。
そして、被相続人が孤独死していたり、生活保護を受けていた、または借金をしていたりすると、警察や市役所、債権者が相続人を調査し、被相続人死亡からある程度時間が経った後に、連絡が来ることがあります。
この場合、通知を受けた日が熟慮期間の起算点となります。
4 先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った場合
別の類型として、先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けた場合です。
相続には順位があり、子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順に相続が発生します。
第一順位の相続人である子がいないか、子全員が相続放棄をするまで、第二順位の相続人である直系尊属は相続人にはなりません。
子全員が相続放棄を完了して、初めて直系尊属は相続人となります。
子が相続放棄をした後、子本人やその代理人等から相続放棄をした旨の連絡を受けた日を以て、相続の開始を知った日となります。
そのため、この日から3か月間が熟慮期間となります。

相続放棄は具体的にどこで行うのか
1 相続放棄の手続

法律上の相続放棄を行う場合、相続放棄申述書というものを作成し、必要な書類を添付の上、収入印紙や予納郵券とともに裁判所へ提出します。
相続放棄は、裁判所で行う手続きであり、裁判所が相続放棄申述を受理して初めて成立します。
これに対して、他の相続人に対して遺産を相続しない旨を伝え、そのような内容の遺産分割協議書を作成することがあります。
これは法律上の相続放棄に対して、事実上の相続放棄と呼ばれることがあります。
2 相続放棄手続を行う裁判所
相続放棄手続は、家事に関わる手続きなので、家庭裁判所で行います。
ただし、どの家庭裁判所でも手続きを行えるわけではなく、書類提出先の家庭裁判所は決まっています。
相続放棄の書類を提出する先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所がどこになるのかは、家庭裁判所のウェブサイトで確認できます。
3 被相続人の最後の住所地について
では、被相続人の最後の住所地とは、具体的にはどの住所を指すのでしょうか。
相続放棄の手続きを行う際、相続放棄申述書の添付資料として、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要となります。
この住民票除票または戸籍の附票には、被相続人の最後の住所地が書かれています。
この住所地が、被相続人の最後の住所地とされます。
時折、実際に被相続人が最後に住んでいた場所と、被相続人の住民票除票または戸籍の附票上の住所が異なっていることがあるため、注意が必要です。
住民票除票は、住民票上の住所が分からないと、請求・取得することができません。
そこで、被相続人の本籍地の市区町村に対して被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を取得する際に、同時に戸籍の附票を取得することで、被相続人の最後の住所地が判明するので、管轄の裁判所の調査をすることができます。

次の相続人のことが気になる方へ
1 相続には順序がある

相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2系統があります。
⑴ 配偶者相続人
配偶者相続人、すなわち被相続人の夫や妻といった配偶者は、常に相続人になります。
⑵ 血族相続人
他方、血族相続人には順位があり、第1順位は被相続人の子、第2順位は
被相続人の直系尊属、第3順位は被相続人の兄弟姉妹になります。
まず、被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。
子には実子のほか、養子も含まれます。
被相続人に子がいない場合や、すべての子が相続放棄をした場合、次は両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
被相続人の直系尊属がすでに死亡している場合、またはすべての直系尊属が相続放棄をした場合、次は兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人と父母が同じ兄弟姉妹のほか、父母の一方が同じ兄弟姉妹も相続人となります。
先順位の相続人が存在している場合(すでに死亡している場合ではない場合)、先順位の相続人全員が相続放棄をするまでは、後順位の方は相続人にならないという点に注意が必要です。
このことは、相続放棄の手続きを行ううえで大切なルールとなります。
2 次順位相続人の相続放棄
先順位の相続人と次順位の相続人が同時に相続放棄の手続きを行うことはできません。
次順位の相続人は、先順位の相続人が全員相続放棄をしてはじめて相続人になるからです。
次順位相続人の相続放棄の熟慮期間は、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを次順位相続人が「知った時」から開始します。
先順位の相続人全員が相続放棄をした時点から進行するわけではありません。
もし、先順位の相続人全員が相続放棄をした時点から熟慮期間が進行してしまいますと、次に説明するように、先順位相続人と疎遠な次順位相続人が相続放棄をする機会を失う可能性があり、酷な結果となってしまうことから、相続放棄の熟慮期間は先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを次順位相続人が「知った時」から開始することとされています。
そのため、疎遠になりがちな第3順位の兄弟姉妹が先順位相続人の相続放棄によって相続人となっていた場合、被相続人の死亡から数年以上経過した後に、ご自身が相続人となったことを知り、相続放棄の手続きを行うということも珍しくありません。
このように、次順位相続人の熟慮期間は先順位相続人が全員放棄をしたことを知った時から進行しますので、先順位の相続人が相続放棄を終えた後、次の順位の相続人への連絡をするタイミングには注意が必要です。
次順位相続人の方が海外にいたり、お仕事等で多忙な時期であったりすると、相続放棄手続を進めることが非常に大変になってしまうためです。
このような場合は、次順位相続人の状況に応じて連絡の時期を遅らせるとよいでしょう。
実務上は、次順位相続人と疎遠な場合、連絡先もわからないこともあります。
このような場合、無理に相続放棄をした旨を連絡する必要はないという判断をすることもあります。
なお、相続放棄をした先順位相続人が被相続人の遺産を管理している場合は、遺産の管理を引き継いでもらうためにも次順位相続人への連絡は必要ですが、管理している遺産がない場合は、次順位相続人への連絡は必須とまでは言えません。
ただ、被相続人に負債がある場合、金融機関等から次順位相続人に連絡が行くことになるのが通常ですので、その連絡が行く前に、相続放棄の事実を知らせてあげるとよいでしょう(相続放棄を弁護士に委任している場合は、弁護士から連絡することも可能です)。

法律上の相続放棄と事実上の相続放棄
1 法律上の相続放棄

厳密な意味での相続放棄は、法律に定められた要件・手続きを満たして初めて実現します(法律上の相続放棄、と呼ばれることがあります)。
その効果は、はじめから相続人ではなかったことになることです。
すなわち、被相続人の財産(負債含む)に関し、法律上全く無関係になります(例外的に、次順位の相続人に引き渡すまで、管理義務が残ることはあります)。
被相続人の負債について、法律上全く無関係になれるという点は、後述する事実上の相続放棄と比較し、非常に重要なものとなります。
被相続人が債務超過に陥っている場合、法律上の相続放棄をすることで、相続債務の負担を免れることができるためです。
法律上の相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に、相続放棄の申述に必要な書類を収集・作成し、これらを管轄の家庭裁判所へ提出した後、家庭裁判所によって相続放棄が受理されることで実現します。
法律上の相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
相続は、被相続人の死亡によって開始されます。
このことから、法律上の相続放棄を被相続人の生前に行うことはできません。
なお、混同しやすい制度として、遺留分の放棄があります。
遺留分の放棄は、相続放棄とは異なり、被相続人の生前に行うことが可能です。
ただし、裁判所の許可が必要であり、認められるために満たすべき要件も厳格です。
2 事実上の相続放棄
法律用語ではありませんが、上記の法律上の相続放棄に対する概念として、事実上の相続放棄というものがあります。
これは、他の相続人に対して相続財産を取得しないことを伝えたり、何も相続しない旨の遺産分割協議(遺産分割協議書に署名押印はするが、財産の取得を定める条項には登場しない)を行うことの総称です。
法律上の相続放棄と事実上の相続放棄は、相続財産を取得しないという点では、効果は同一です。
他方、相続債務に関しては、法律上の相続放棄と、事実上の相続放棄とで大きく異なります。
法律上の相続放棄は、先述の通り、法的に相続人でなかったことになりますので、被相続人の負債(の一部)を負うことはありません。
しかし、事実上の相続放棄は、仮に相続人間においては相続債務を負わない旨を定めたとしても、これは相続人の間でしか効果がありません。
可分債権である金銭債権は、相続開始と同時に法定相続割合に応じて分割されますので、債権者からみると、すべての相続人に対し、それぞれの法定相続割合に応じて支払いを求めることができます。
このように扱われないと、債権者側の立場としては困ってしまいます。
支払い能力のない相続人にすべての相続債務を集約されてしまうと、債権の回収をすることが困難になってしまうためです。
そのため、被相続人が債務超過に陥っており、相続債務の負担から免れる必要がある場合には、必ず法律上の相続放棄を選択する必要があります。

相続放棄が認められなくなるケース
1 法定単純承認事由に該当する行為

相続放棄に関連する用語のひとつに、法定単純承認事由というものがあります。
法定単純承認事由に該当する行為を行うと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為のひとつとして、相続財産の処分が挙げられます。
相続財産の処分という言葉は抽象的で、広い意味を持ちますが、実務上よくあるケースとしては、相続財産の廃棄・売却・費消、遺産分割協議が挙げられます。
これらの行為は、本来的には、相続財産を相続によって取得した人にしかなしえない行為です。
そのため、これらの行為を行った場合、相続人として相続財産を相続する意思があったとみなし、相続放棄が認められなくなることがあるのです。
2 相続財産の廃棄・売却・費消
相続財産の廃棄・売却・費消は、いずれも「処分」に該当しえます。
売却とは、具体的には、不動産や、自動車、高級時計等の、価値のある財産を売却し、金銭に換えてしまう行為です。
もし売却してしまった後で相続放棄の手続を行わなければならなくなった場合、とにかくすぐに買手へ連絡し、錯誤を理由として元に戻してもらうよう相談しましょう(もっとも、相手のいる話なので、必ずしも元に戻せるとは限りませんので注意が必要です)。
費消については、典型的なものは、被相続人の現金や預貯金を、相続人自身のために使うことです。
これも基本的には処分にあたる行為となりますが、例外として、社会通念上相当な金額の範囲内で、被相続人の葬儀に使用することは認められる場合があります。
必要に応じて葬儀に使用した金額等の説明ができるように、葬儀の際の領収証等を保存しておくことが大切です。
廃棄も、処分に該当します。
被相続人が生前使用していた衣類や家財道具などの日用品類の処理において、問題になることが多いです。
実務上、換価価値がなく、むしろ処分にお金がかかる残置物については、財産的価値がないことから相続財産を形成しないと解釈し、廃棄をしても問題となることはあまりありません。
しかし、明文や裁判例で明確に認められているわけではないので、注意が必要です。
被相続人が所有していた建物についても注意が必要です。
特に老朽化が進み、倒壊等のおそれがある場合に問題となります。
取壊しは廃棄に該当しますので、相続放棄をする場合には、取り壊すことはできません。
倒壊を防ぐための最低限の補修をすることは問題ありません。
3 遺産分割協議
遺産分割協議は、相続財産を取得する意思を表明する行為であるという趣旨から、処分に該当する行為と考えられています。
そのため、遺産分割協議を行ってしまうと、基本的に相続放棄は認められないことになります。
しかし、実務上は、遺産分割協議を行ってしまった後になって多額の相続債務が発見されることもあります。
このような場合、仮に相続債務の存在を知っていたならば遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたという事情が認められれば、錯誤を理由に遺産分割協議を取消し、相続放棄が可能となると解釈される場合があります。

債権者対応もおまかせください
1 被相続人が借金をしていた場合

被相続人が、貸金業者や銀行などからお金を借りていた場合、そしてそのことを家族に内緒にしていた場合がよくあります。
被相続人が亡くなると支払いが止まるため、債権者である貸金業者や銀行等は、被相続人宛てに支払いを催促する手紙を送ったり、電話をかけたり、時には自宅を訪問したりすることがあります。
債権者側が被相続人死亡の事実を知らない場合は、被相続人の名義で書面等が送られてくることもあります。
または、債権者が被相続人が死亡したことを知り、相続人を調査したうえで、相続人の住所へ催促の手紙を送付することもあります。
被相続人と相続人が疎遠であり、相続人が被相続人の死亡の事実を知らないような場合には、このような形で債権者から相続人に対する書面が届くことが多いです。
債権者が弁護士に依頼して、相続人に対して支払いを請求することもあります。
相続人としては、弁護士から突然書面が送られてくることになるので、とても不安な気持ちになります。
このようなことがきっかけで、被相続人に相続債務が存在していることが判明します。
また、具体的に請求を行ってきた債権者以外にも債権者がいる可能性もあります。
網羅的に債権者や債務額を調査するには、CICやJICCなどの信用情報機関へ問い合わせをすることになります。
2 相続放棄検討段階~相続放棄手続中の債権者対応
相続放棄をすることを決めた後の債権者への対応は、2通りの方法が考えられます。
1つ目は、一切無視するというものです。
もっとも、これはあまりおすすめしません。
債権者によっては、相続人を相手に訴訟を提起することも考えられるためです。
2つ目は、債権者に、相続放棄を検討している旨を伝えることです。
相続放棄を弁護士に依頼すれば、その弁護士を通して伝えることもできます。
弁護士を通した方が、よりスムーズに話が進むことも多いです。
債権者側の立場としては、相続人本人が相続放棄をすると言っていても、信用し切れない部分があります。
しかし、相続放棄の依頼を受けた弁護士からの連絡があった場合、債権者としても信用しやすいため、請求を一旦止めてくれることが多いです。
3 相続放棄申述受理後
相続放棄の申述が裁判所に受理されることにより、相続放棄は完了します。
相続放棄が完了したら、その旨を債権者に伝えます。
通常、債権者は相続放棄の連絡を受けたことにより、回収不可能と判断して処理を進めます。
この意味で、相続放棄が完了したことを債権者に伝えてあげることは、とても大切です。
具体的には、相続放棄が完了した際に裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書の写しを、債権者に渡します。
FAXで対応している業者もあれば、郵送して欲しいという業者もいますので、要望に沿った対応をします。
債権者としても、相続放棄申述受理通知書の写しが手に入ると、社内決裁などに使用できるため、円滑に請求をストップすることができるのです。
当法人では、債権者に連絡するのが怖いという方のために、相続放棄に関する手続きが完了した後、債権者へ連絡の上、相続放棄申述受理通知書の写しを提供し、以降の請求が起きないようにする等、債権者への対応も行っております。

相続放棄を検討したほうがよい事例
1 被相続人が債務超過である可能性があるケース

被相続人の債務超過を理由に相続放棄をされる方は、少なくありません。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったことになる手続きです。
その効果は絶大であり、被相続人が負っていた債務を、租税債権も含め、免れることができます。
被相続人には、不動産や預貯金などの資産はほぼ無く、貸金業者からの借入やローン、税金の滞納等の負債のみが残っているということもよくあります。
また、相続放棄の場面で非常に多いのが、被相続人の遺品の中から貸金業者からの請求書が発見されるケースや、債権者を名乗る者から連絡が来たりしたことで、相続債務が存在することが判明するケースです。
こういったケースの場合、負債の全体像が明確ではなく、具体的に誰に対してどのくらいの相続債務を抱えているか不明なことが多いと言えます。
このように「多額の負債を有しているおそれ」があることも、相続放棄の理由となります。
実務上は、相続人は被相続人と疎遠であり、被相続人が住んでいた場所すら知らず、事実上調査が困難な場合など、被相続人の財産状況について詳しく知らないということも多いです。
このような場合、被相続人が誰に対して、どの程度の債務を負っているかが分かりません。
後でどのような請求がされるかわからないという懸念を払しょくするため、相続放棄を選択するということが多いです。
2 2 相続に関わりたくないケース
他の相続人の中に、性格に難があり、話がまったく通じず遺産分割協議を進められないような人がいる場合や、被相続人とは没交渉のまま長年離れた場所で暮らしている場合、あるいは被相続人が再婚して新しい家庭を持っていたため相続に踏み入りたくない・相続する気がない場合などにも、相続放棄の手続を使うことができます。
このような場合、相続放棄が完了したら、相続放棄申述受理通知書の写しなどを他の相続人に渡すことをおすすめします。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を発生しません
そのため、相続放棄により相続人から外れた旨を客観的に証明できるようにしておく必要があるからです。
特に、金融機関における預金の名義変更や、不動産の登記手続きの場合においては、相続放棄申述受理通知書の写しや、相続放棄申述受理証明書が重要になります。
補足をしますと、相続放棄をした事実は、戸籍謄本類には反映されません。
遺産を特定の相続人に集中させたいケース
遺産分割協議でも、特定の相続人が、負債を含めてすべての財産を相続するとすることで、他の相続人が相続放棄をした場合と似た効果を発生させることができます。
これは、裁判所に対して行う法律上の相続放棄に対し、事実上の相続放棄と呼ばれることもあります。
もっとも、法律上の相続放棄と事実上の相続放棄とでは、大きく異なる点が2つあります。
1つは、債務について、債権者には対抗できないという点です。
金銭債務は、法定相続割合に応じて分割されます。
そのため、相続人同士の間においては債務を特定の相続人が負担すると定めていても、債権者から見ると、法律上はそれぞれの相続人に対して法定相続割合に対応した金額の請求ができてしまいます。
つまり、相続財産は取得できないのに、債務は一部負担しなければならないという状況が発生してしまいます。
これを回避するには、債権者の同意のもと、免責的債務引受契約を締結するなどの対応をしなければなりません。
もう1つは、遺産分割協議後に新たに遺産が発見された場合、再度遺産分割協議を行わなければならないことです。
相続放棄をすれば、法的に初めから相続人でなかったことになりますので、上記2つの問題は根本的に解消されます。
他には、先祖代々の土地を分散させないため等の理由で、家業を継ぐ相続人に負債も含めた全ての財産を集中させるという考えのもと、他の相続人全員が相続放棄をするということもあります。

相続放棄申述書提出後の注意点
1 相続放棄申述書提出後の流れ

相続放棄は、相続放棄申述書を始めとして、必要な書類を裁判所に提出することで手続きが開始されます。
また、提出した時点で、基本的には期限内に相続放棄の申述をしたことになります。
もっとも、相続放棄申述書を提出しても、手続きが開始されるにすぎません。
提出した時点で相続放棄が完了するわけではないので、注意が必要です。
相続放棄申述書が提出されると、裁判所は資料等を参照し、相続放棄を認めてよいか否かの審査を開始します。
あまり知られていませんが、実は相続放棄は相続放棄申述書を提出した後にも、裁判所に対する手続きがあります。
具体的には、質問への回答と、審問です。
これらは、裁判所の裁量によって実施されるか否かが異なるため、必ずしも行われる手続きではありません。
しかし逆の見方をすれば起きる可能性があるということですので、知っておくべきです。
2 質問への回答
審査を開始した後、裁判所は、申述人(相続放棄手続をしている相続人)に対して質問状を送付します。
質問状を送る目的は、以下の2点を確認することであると考えられています。
①相続放棄の申述が申述人の真意に基づくものであるか
②申述人が法定単純承認事由に該当する行為を行っていないか
質問状に記載されている質問は、相続放棄申述の経緯や時期などについてですが、裁判所によって異なります。
1、2問程度の簡単な質問しかされない場合もあれば、10問以上の質問がなされることもあります。
回答の仕方次第では、相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、回答の記載は慎重に行う必要があります。
また、質問状の送付先は、多くの場合、次の3つのパターンのうちのどれかです。
①申述人本人に対して申述人の住所へ送付する
②代理人弁護士がいる場合は代理人弁護士宛に送付する
③代理人弁護士がいる場合に限り質問状を送らない
②のパターンであれば、代理人弁護士が回答を作成し、裁判所へ返送します。
③のパターンであった場合は、質問状対応の巧拙により相続放棄が認められなくなるリスクがありません。
質問状への回答の仕方次第では、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、相続放棄における質問状対策は弁護士に相談しましょう。
そのほかの例としては、裁判所から代理人弁護士に対して電話による照会がなされ、弁護士が口頭で回答するというものもあります。
また、まれに申述人本人宛の質問状が代理人弁護士のもとに届くこともあります。
この場合、代理人弁護士から申述人本人へ転送します。
3 審問
審問とは、裁判所が申述人や代理人を裁判所へ呼んで、相続放棄に至る事情について、裁判官が質問をすることをいいます。
なお審問は、電話で行われることもあります。
相続放棄において審問がなされることは少ないですが、法定単純承認事由に該当する行為が存在する可能性が高い場合など、裁判所が相続放棄を受理するべきか判断するために詳細な情報が必要とされる場合に開催されます。
審問になった場合、裁判官の質問に的確に回答する必要があり、かつ相続放棄申述書に記載した内容と矛盾がないようにしなければなりません。
審問がなされる場合というのは、相続放棄に至った事情が複雑な場合や、相続放棄が認められない事情の存在が疑われる場合ですので、裁判官に対する質問への対策をしっかり行う必要があります。
代理人弁護士がいる場合、審問の場に同行し、立ち合うことができます。
専門的な質問に対しては、代理人弁護士が代わりに回答することもできます。
審問になった場合や、審問になることが予想されるような場合は、弁護士へご相談ください。

相続放棄手続ではどのような書類が必要なのか
1 相続放棄に共通して必要となる書類
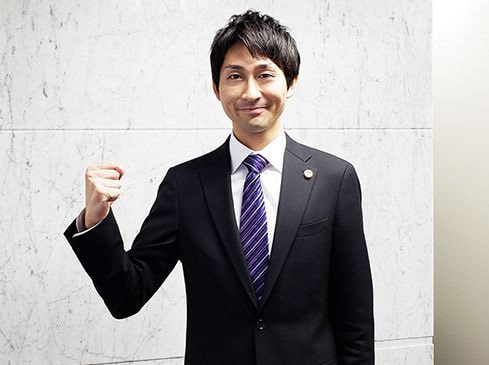
相続放棄をする際には、以下の書類を必ず取得することになります。
・被相続人の除籍謄本(死亡の記載のある戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・相続放棄を申述する相続人(申述人)の戸籍謄本
申述人が被相続人の配偶者であったり、戸籍から抜けていない子であったりする場合、被相続人の除籍と相続人の戸籍が一つの戸籍謄本に載っていることもあります。
このような場合、1通の戸籍で被相続人の除籍謄本と申述人の戸籍謄本を兼ねることができます。
2通用意する必要がないため、費用も抑えられます。
戸籍の附票という書類は、聞き慣れない方も多いと思います。
戸籍の附票は、住所の履歴が記された書類です。
被相続人の最後の本籍地で取得可能であるため、除籍謄本を取得する際に、同時に申請することができます。
最後の本籍地と最後の住所地が異なる自治体である場合、戸籍の附票の方が簡易に取得できます。
2 子が亡くなった場合の直系尊属の場合
上記1に加え、次の書類が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
この場合、収集する戸籍謄本類が他のケースに比べて多くなるため、注意が必要です。
子が結婚するなどして親の戸籍から抜けており、本籍地を別の自治体に移している場合、複数の自治体に対して戸籍の申請をしなければなりません。
戸籍謄本類の収集に必要な期間を考慮し、早めに着手するのがよいでしょう。
3 兄弟姉妹の相続放棄の場合
上記1に加え、次の書類が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
この場合も、戸籍謄本類の収集に必要な期間が長くなるため、注意が必要です。
直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本については、裁判所によって運用は異なるものの、出生年月日から見て一定年齢(例えば115歳など)に達していると考えられる方については、死亡の記載のある戸籍謄本の提出は不要とされることもあります。
4 代襲相続人が相続放棄をする場合
1または2または3に加え、次の書類が必要です。
・被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
代襲相続人が相続放棄をするケースは、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人であることが多い傾向にあります。
亡くなった方が高齢である場合、その兄弟姉妹も高齢であり、先に亡くなっていることがあるためです。
このケースですと、上記の兄弟姉妹相続以上に戸籍の収集に時間がかかることがよくあります。
5 被相続人死亡日と、相続開始を知った日が異なる場合
・被相続人死亡の事実が書かれた市役所からの通知書や、債権者からの支払い請求書など
一般的には、被相続人の死亡の事実は、被相続人の死亡日当日か、その数日後に知ることが多いと考えられます。
もっとも、被相続人と疎遠であったり、海外に長期滞在していたりしていたなどの事情により、長期間被相続人の死亡の事実を知り得ないこともあります。
典型的な例として、疎遠で音信不通であった親が借金を残したまま亡くなっていたというものがあります。
死亡日から1年程度経過した後に、親の債権者が相続人を調べ、相続人に対して支払い請求をすることがあります。
税金や社会保険料等の滞納があった場合には、市役所などから支払い請求がなされます。
相続人は、この時に初めて被相続人の死亡の事実を知ることになります。
相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月以内に行えばよいので、債権者や市役所等から送付された書面を読んだ日をもって、相続の開始を知ったと説明することになります。
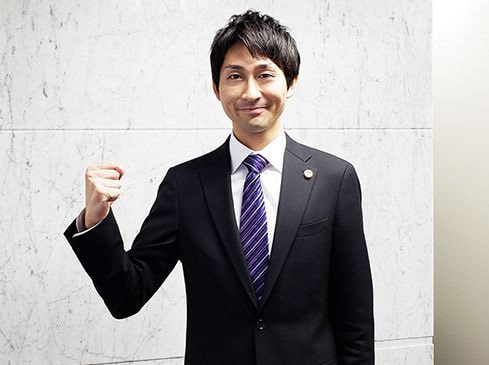
もし相続財産に手を付けてしまった場合は
1 遺産を売却換価してしまった場合

遺産の中には、財産的価値のあるものがあります。
その典型的なものとして、被相続人の自宅の土地や建物といった不動産のほか、自動車、貴金属類などが挙げられます。
これらの財産を売却し換金する行為は、法定単純承認事由に該当する行為とされており、売ってお金に換えてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
万が一これらの財産を売却してしまっていた場合、原則として相続放棄は困難となります。
しかしながら、売却先に事情を説明した上で、売買契約を無かったことにして、返金するとともに売却した財産を返してもらえることもあります。
どうしても相続放棄をしなければならない事情がある場合には、諦めずに売却先と交渉する価値はあります。
2 遺産分割協議をした場合
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名押印をして遺産分割を完了させる行為は、被相続人の遺産を取得する意思の現れとされます。
これも、法定単純承認事由に該当する行為と考えられ、原則として相続放棄は認められないことになります。
一方、遺産分割協議後に、相続債務が発見されるという場合もあります。
被相続人が他の債務者の連帯保証人となっていた場合などでは、主債務者が支払いを滞納するまでは債権者からの連絡が来ないことが多く、遺産分割協議を終えるまでの間には発覚しないこともあります。
このような場合、相続債務の存在を知っていたならば遺産分割協議をしなかったということで、遺産分割を錯誤無効とすることで、法定単純承認事由に該当する行為が消滅する結果、相続放棄が可能となる場合があります。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄をお考えの方はご相談ください
相続放棄というのは遺産を一切受け継がないという意思表示をする手続きで,たとえば亡くなった方が財産よりも借金の方を多く残していた場合などに使用されることがあります。
相続放棄の手続きに不備があるなどして相続放棄が認められなかった場合,思いもよらない損害が生じてしまうおそれがありますので,手続きには注意が必要です。
相続放棄をするにあたっては,亡くなった方などの戸籍や申述書といった,さまざまな書類が必要となります。
期限内にそれらを漏れなく用意し,スムーズ,かつ,適切に相続放棄をおこなうためにも,一人で行うのではなく,弁護士に依頼されることをおすすめします。
当法人では,相続放棄に関するご相談を原則として相談料無料で承っております。
相続放棄をお考えの方はもちろん,どうするかお悩みの方も,一度当法人までご相談ください。
相続案件を得意とする弁護士がお話をお伺いし,ご説明やご提案等をさせていただきます。
夜間のご相談もしていただくことができますので,お仕事の帰りなどにも相続放棄についてご相談いただけます。
お役立ちリンク